夫が無職で働いてくれない場合、「すぐにでも離婚したい!」と考える方も多くいらっしゃるでしょう。
無職の夫と離婚する場合でも、妻が慰謝料や婚姻費用などの金銭的負担をしなければならないのでしょうか。
この記事では、無職の夫との離婚を考えている方に向けて、
- 夫が働かないことは離婚原因になるのか
- 無職の夫と離婚する際の離婚条件をどのように決めるか
について解説します。
夫が働かないことは離婚原因になるか

夫が離婚に反対している場合、裁判所での離婚を認めてもらうには法律上の離婚原因が必要です(民法770条)。
法律上の離婚原因としては、次の5つがあります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
単に無職であることは、どれにも当てはまらないため法律上の離婚原因とはなりません。
ただし、夫が働かないことの原因が怠け心からくるもので働かない期間が長くなれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性はあるでしょう。
なお、離婚するために法律上の離婚原因が必要となるのは、あくまで夫が反対している場合のみです。
夫が協議離婚や調停離婚に応じるのであれば、法律上の離婚原因がない場合でも離婚はできます。
無職の夫と離婚する際の離婚条件

無職の夫と離婚するときでも、通常の離婚と同じく離婚の条件を決める必要があります。離婚の際に決めるべき離婚の条件としては、次のものが挙げられます。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 年金分割
- 面会交流
また、離婚前に別居するときには婚姻費用の分担も問題となります。
ここからは、それぞれの条件について、夫が無職であることをどのように考慮すべきかについて解説します。
財産分与
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を夫婦で分ける制度です。
婚姻生活で築いた財産は、現在夫が無職であったとしても、原則として財産分与の対象となります。
財産分与の割合は、2分の1ずつが原則です。
ただし、夫が婚姻期間中を通じて無職の状態で、家事への協力もしていなかったような場合には、2分の1以外の割合を検討する余地があります。
なお、財産分与の対象となるのは、あくまで夫婦の協力のもとで築かれた財産です。
婚姻前から持っていた預貯金や親から相続した財産などは財産分与の対象とはなりません。
慰謝料

慰謝料は、離婚の際に常に発生するものではありません。
慰謝料が発生するのは、不貞行為、DV、モラハラ、生活費を渡さない悪意の遺棄など夫婦の一方に不法行為があった場合のみです。
無職の夫と離婚する場合でも、妻に慰謝料発生の原因となる不法行為がないのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。
一方、妻に不法行為やDVなどがあったときには、たとえ夫が無職であったとしても、慰謝料を支払わなくてはなりません。
夫が怠けて働かず生活費を渡してくれないだけでなく、家事もしないといった状況が長く続いた場合には、「悪意の遺棄」にあたるとして夫に慰謝料を請求できる可能性があります。
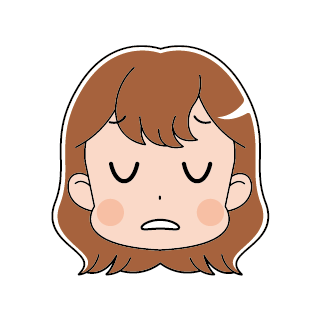
ただし、実際には無職の夫から慰謝料を回収するのは難しいでしょうね…。
親権・養育費
夫が無職で妻が働いているという状況であれば、夫が親権を争ったとしても、妻に親権が認められるのが通常です。
妻が親権者になった場合には、無職の夫でも養育費を負担する義務を負います。
ただし、無職の夫から養育費の支払いを受けるのは難しい場合が多いでしょう。
無職の夫から慰謝料を受け取りたい場合には、就職までの猶予期間を与えたうえで数か月後から養育費の支払いを開始させるなど、離婚の際にしっかりと話し合っておくことが重要です。
養育費の金額については、夫が潜在的にどのくらいの収入を得られる見込みがあるのかを考慮して決めるのが良いでしょう。
夫が養育費の支払いを了承したときには、口約束ではなく、必ず公正証書を作成しておくようにしましょう。
公正証書とは、公証役場で作成する公文書です。
公正証書を作成しておくと、夫が養育費の支払いを怠ったときに、預金口座や給与の差押えができるようになります。
年金分割・面会交流

年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に納付した額に対応する年金を分割して、夫婦それぞれの年金として扱う制度です。面会交流とは、離婚後に子どもと別居している親が子どもと会うことを言います。
年金分割や面会交流の条件を決めるに際しては、夫が無職であることは考慮されません。
面会交流は、離れて暮らす親が養育費などの金銭的負担をしているか否かにかかわらず認められる権利なので、夫が無職であるからといって面会交流を拒絶することはできないのです。
婚姻費用
離婚が成立するまでに別居する場合には、婚姻費用の分担も問題となります。
婚姻費用は、収入の多い方が負担するのが原則です。夫が無職の場合には、妻が夫に婚姻費用を支払うことになります。
ただし、夫に働いて賃金を得る能力があるにもかかわらず、自分の意思で働こうとしない場合には、潜在的な労働能力を考慮して、婚姻費用の分担を避けられる可能性もあるでしょう。
なお、夫の手元にお金がなく、弁護士に相談する行動力もないようなケースでは、そもそも婚姻費用を請求されない可能性もあります。
まとめ

無職の夫と離婚する場合でも、離婚原因が必要です。
夫がどうしても離婚に応じないときは、無理やりにでも別居して自ら「婚姻を継続し難い事由」を作り出すのも1つの方法です。
離婚条件の話し合いについても、無職の夫が相手では上手く進まないこともあるでしょう。
本人同士の話し合いで離婚できないときは、
- 弁護士に相談する
- 離婚調停を利用する
などの手段を検討することをおすすめします。
この記事で解説した離婚条件は、あくまでも夫が自分自身の権利を主張したときに適用されるものです。
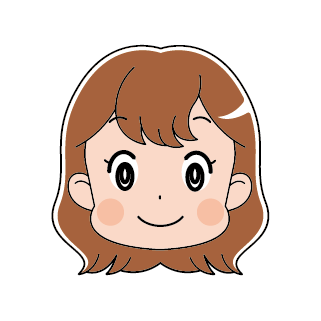
無職の夫が弁護士にも弁護士にも相談せず、自分の権利も主張しないような場合には、金銭的負担なくスムーズに離婚を進められる可能性もありますよ!



コメント